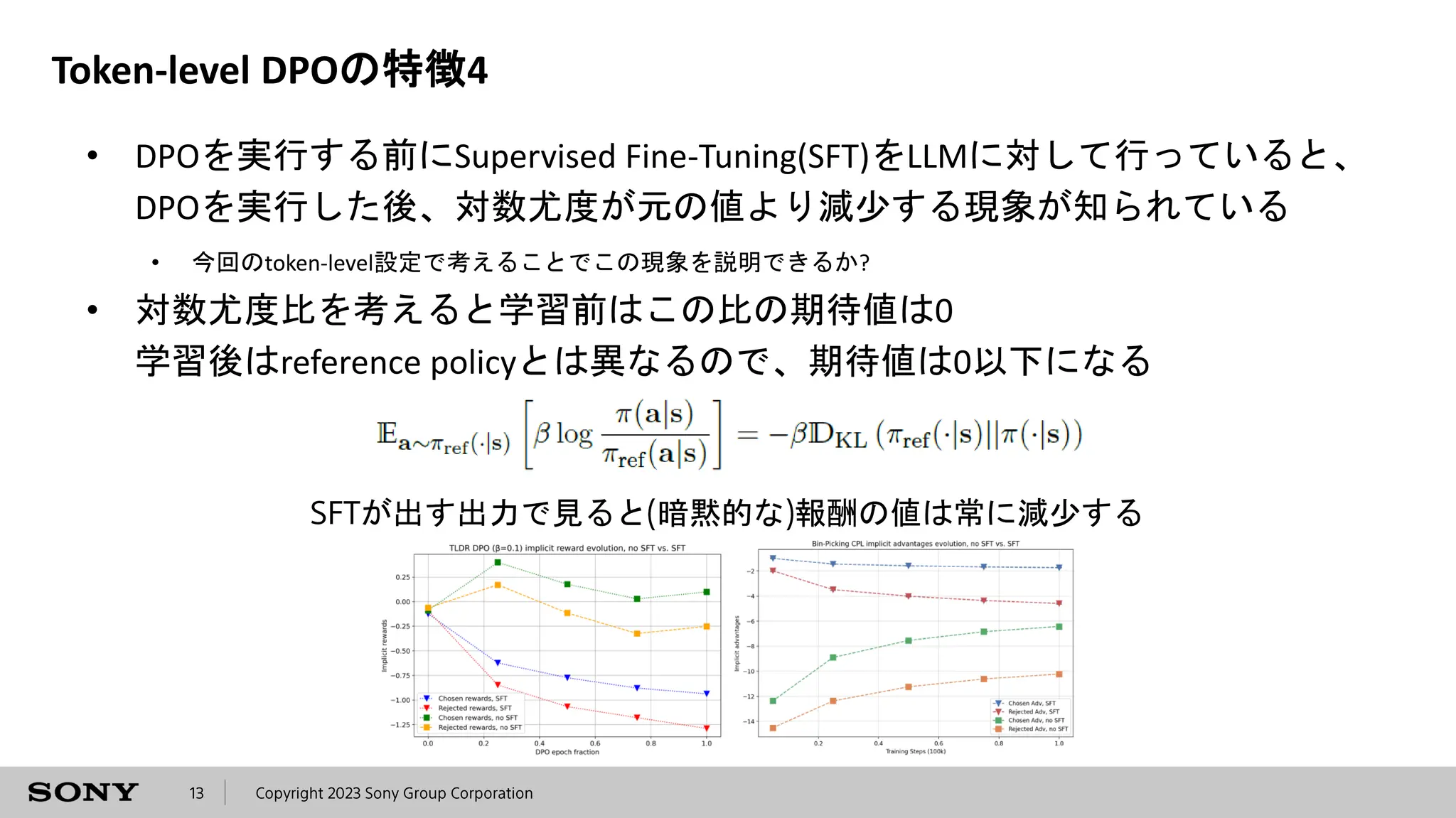YouTube nnabla channelの次の動画で利用したスライドです。
【AI論文解説】RLHF不要なLLMの強化学習手法Direct Preference Optimization(+α)
https://youtu.be/s4OqzfDyjXY?si=nnDFza9x1SGkTgCX
以下の論文を解説しています。
From r to Q∗: Your Language Model is Secretly a Q-Function
https://arxiv.org/abs/2404.12358






![報酬関数を方策関数を使って表現2
• Max-Entropy RLでの最適方策は以下の形式で表現できることが知られている[1]
価値関数はエントロピー項の影響で
あまりみない形になる
初見ではなぜこうなるのか全く分からないと思いますが、↑の定義の下、 と は以下のような関係に
ここでさらに、割引率 で状態遷移が決定的だと仮定すると、報酬関数、 関数、 関数は次の関係にある
の報酬 でのペナルティ](https://image.slidesharecdn.com/rlhfllmdirectpreferenceoptimization-250718030816-dd085d52/75/AI-RLHF-LLM-Direct-Preference-Optimization-7-2048.jpg)