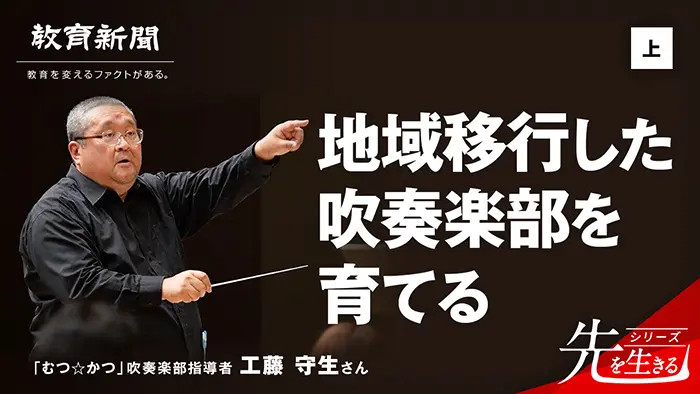伝統的なカトリック系ミッションスクールだった宇都宮海星女子学院中学・高校は、2023年度に星の杜中学・高校として生まれ変わった。世界10都市以上で海外留学を経験できる制度の導入など積極的にグローバル教育に取り組み、入学希望者も年々増加するなど注目を集めている。また、24年度には全国の私立中学・高校12校とコンソーシアムを立ち上げ、国内留学などの連携も始めた。これらの施策を推進する小野田一樹校長に、学校改革の現状や、私学を中心としたこれからの学校教育の在り方などを聞いた。

北関東唯一のカトリック系ミッションスクールとして70年以上にわたり厳格な教育活動を行ってきた宇都宮海星女子学院中学・高校が、2023年4月に共学の「星の杜中学・高校」として新たに開校した。少子化の影響もあり年々減少していた生徒数も、この学校改革を機に増加に転じた。改革を推進したのが、24年度から校長を務める小野田一樹氏。民間の旅行会社で教育事業に携わってきたという小野田氏に、同校の学校改革に携わることになった経緯や、学校改革の現状、思い描く教育の将来像などを聞いた。

フィンランドで10年以上、いわゆる障害のある子への支援や福祉に関して広く研究を重ねる矢田明恵さん。インタビュー後編では、同国でインクルーシブ教育の推進により増加したとされる不登校の現状や、同国との比較で見る日本の学校教育の良さと今後の展望などを聞いた。

「フィンランドも永遠に模索し続けている。決してユートピアや天国のような場所ではない」と語るのは、心理士として日本の学校などで勤めた後、現在は同国で研究者を務める矢田明恵さんだ。障害のある子への支援や福祉を専門とする矢田さんに、インタビュー前編では、同国でのインクルーシブ教育の現状や課題などを聞いた。

大相撲九重部屋の千代の海関、本名・濵町明太郎さんは2024年の引退後、同年10月から東京都立農産高校で保健体育講師を務めている。中学時代の相撲部の顧問の先生たちの、学業優先の姿勢や生徒との接し方に尊敬の念を抱き、教員を目指したという濵町さん。顧問の先生の出身校だった日本体育大学に入学し、相撲部で活躍しながら教員を目指していたが、卒業後にプロの世界へと進路を大きく変更する。インタビュー後編では、プロに進路を変えた理由や、相撲部屋で感じた人を育てることへの思い、再び教員を目指した経緯などを聞いた。

大相撲九重部屋の千代の海関が、2024年6月に惜しまれながら力士生活に幕を閉じた。本名・濵町明太郎さんが引退後に選んだ職業は高校の保健体育科の教員。同年9月から東京都立足立新田高校で時間講師を務め、10月からは東京都立農産高校で保健体育を週9時間受け持ちながら、7月の東京都の教員採用試験を目指して勉強を続けている。もともと、中学生の頃から教員に憧れていたという濵町さん。大相撲の世界から、改めて教員になりたいと考えたのはなぜか、どこに魅力を感じているのかを聞いた。

探究学習のプログラム開発と支援を手掛ける㈱ミエタの創業者である村松知明さんは、大企業での国際的なキャリアを経て教育分野に転身した。動機は日本企業の世界的なビジョンの希薄さや、学生時代からの社会参画の必要性を痛感したことにあるという。村松さんは、中高生との関わりを通じて、これからの探究学習は社会で活躍できる資質・能力の育成から、教科の学習意欲を向上させる原動力になると確信している。自身が受けてきた学校教育の課題を乗り越える、新たな教育の可能性を聞いた。

探究が学校教育の新たな柱として注目を集める一方、現場からはカリキュラムへの落とし込みや、指導・支援する教員のスキル向上に苦労する声も聞こえてくる。そんなニーズに応えようと、村松知明さんは㈱ミエタを創業、社会課題解決に挑戦する専門家と生徒をつなぎ、独自の探究学習プログラムを提供する。専門高校魅力化への参画や、働き方改革に特化した人材派遣など、探究と進路を切り口にした学校支援は新しい。学校現場での具体的な取り組みについて聞いた。

アマゾンランキング1位を獲得したデビュー作で、「公教育はオワコンじゃない」と強く訴えたのは、オモロー授業発表会や哲学対話などでも知られる愛知県公立中学校の熊谷雅之教諭だ。インタビューの後半では同教諭に、仕事を楽しむ極意や子どもとの関係づくりの方法を聞いた。

「地域を教育で盛り上げよう」「教育を楽しもう」と訴えるのは、デビュー作『教師は学校をあきらめない! 現場発信 子どもたちを幸せにする教育哲学』でアマゾンランキング1位を獲得した、愛知県公立中学校の熊谷雅之教諭だ。「オモロー授業発表会全国フェス」副実行委員長としても活躍する同教諭に、インタビューの第1回では、地域のつながりを重視する理由や、著書刊行に至る経緯などを聞いた。
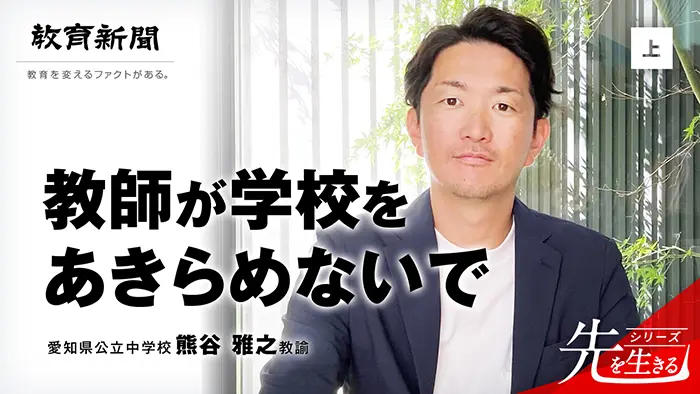
岐阜県飛騨市の全小中学校に設置された「学校作業療法室」に、常駐している作業療法士の奥津光佳さんは、作業療法士を目指して大学で学んでいたときのある出会いをきっかけに、岐阜県内で働き始めたのだという。インタビュー最終回では、「学校作業療法室」がどのような経緯で生まれたのか、さらには、学校現場を回って感じている課題とこれからの目標などを聞いた。
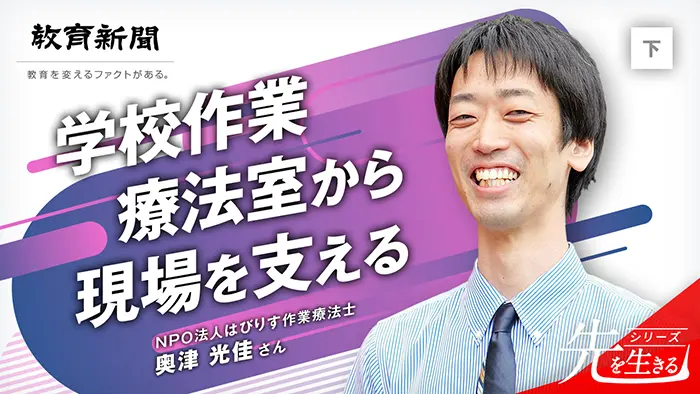
岐阜県飛騨市は2023年度に全小中学校9校に「学校作業療法室」を設置した。月2回のペースで全校を訪問している作業療法士の奥津光佳さんに、インタビュー2回目では教員研修の様子や保護者とのやりとり、相談があった子どもたちにどのように接していくのかなど、具体的な実践内容を聞いた。

日常生活を送るためのさまざまな〝作業〟を通して、心と体のリハビリを行う専門家の作業療法士の実践は、発達障害を含むあらゆる子どもたちへの支援として効果があると言われており、米国などでは当たり前のように学校現場に作業療法士が配置されている。日本の教育界でも少しずつ関心が高まっているが、岐阜県飛騨市では2023年度から全小中学校に「学校作業療法室」を設置した。現在、作業療法士として飛騨市内の学校を毎日訪問している奥津光佳さんに、学校作業療法室での具体的な取り組みを聞いた。

災害の被災地などで学生とともにフィールドワークを重ねている金菱清・関西学院大学教授は、フィールドワークは到達点に向けて解いていくものではないからこそ、「教育の未来を変える」可能性があると語るとともに、失敗から面白さが広がることを味わえるのは「探究の時間」でのフィールドワークだと指摘する。インタビュー第3回では、被災体験を取材することなどフィールドワークをする意味などについて聞いた。

高校の「総合的な探究の時間」が2022年度にスタートしたことを踏まえて、昨年10月に『フィールドワークってなんだろう』を出版した関西学院大学の金菱清教授は、仙台市にある東北学院大学勤務時代に東日本大震災を経験。学生たちと被災地をフィールドワークして、多くの被災者の声を記録してきた。とりわけ、幽霊と出会った話に着目して、さまざまなメディアで取り上げられた。インタビュー第2回では、学生が活動する中で気付いたことなど、フィールドワークの実際の様子を聞いた。

高校の「総合的な探究の時間」が2022年度からスタートしたが、学習を進める上で「フィールドワーク」を導入する例も少なくない。社会学者の金菱清・関西学院大学教授は、東日本大震災や熊本地震の被災地などで、学生と共にフィールドワークを数多く実施してきた。これまでの経験を踏まえ、昨年10月にはフィールドワークそのものに焦点を当てた『フィールドワークってなんだろう』(ちくまプリマー新書)を出版。金菱教授に、フィールドワークの進め方などについて聞いた。

「教師のハッピーが児童のスマイルに」を合言葉に、研修や研究を大きく変えた埼玉県蕨市立北小学校。研究主任などとしてその立役者を務めた葛原順也氏に、インタビューの最終回では、教員が幸せになれる環境の在り方や現場に向けたメッセージを聞いた。

研修や研究の在り方を大きく転換させた埼玉県蕨市立北小学校。研究主任などとして、その立役者を務めた葛原順也氏は「モチベーションベース」にかじを切ったと話す。教員のモチベーションを重視したという同氏に、研修の具体的な事例やアイデアの詳細を聞いた。

教員の仕事を、「やらねばならぬ」から「やってみたい!」へ――。従来の校内研究を一から見直し、「フェス形式」と銘打って実施した研究発表会が大きく注目された、埼玉県蕨市立北小学校。その大転換をけん引したのは、2021年度に同校で研究主任を務めた葛原順也氏だ。「教員の仕事をモチベーションベースに」と語る葛原氏に、研究・研修をアップデートする上で基本とした考え方や、取り組みの成果を聞いた。

GIGA端末と汎用(はんよう)のクラウドツールを最大限に活用し、コストパフォーマンスに優れた校務DXを推進する東京都練馬区立豊玉小学校の鈴木智裕主幹教諭。教職員間や子ども、保護者との情報共有やコミュニケーションが迅速にできるようになれば、自身を含め子育て世代への恩恵は大きいと実感している。だが、さまざまなアイデアの源は職務への責任感からだけではなさそうだ。学校でも家庭でも楽しみを見つける、ミドルリーダーのワーク・ライフ・バランス論を聞いた。

標準のクラウドサービスを使って週案をデジタル化することから校務DXを推進してきた東京都練馬区立豊玉小学校。子どもたちや保護者向けの発信もデジタルにシフトしている。成功の陰には管理職のリーダーシップだけでなく、鈴木智裕主幹教諭の「今は、誰でもデジタル端末で情報を見る前提」という割り切りも必要だった。一気にデジタル化を進めるのではなく、遊び心も取り入れながらDXを進めていくマインドは、校務DXが進まず焦っている担当者の参考になりそうだ。

GIGAスクール構想により学習面でのデジタル活用が大きく前進する一方、全国で後れをとっているのが校務のDXだ。全国の公立小中学校などの自己点検結果によると、効果を実感しているのは「保護者との連絡手段」などにとどまり、DXと呼ぶには程遠い。そんな中、東京都練馬区立豊玉小学校では週案簿をクラウドに集約し、業務の可視化を実行。教務主任を務める鈴木智裕主幹教諭を中心に働き方改革を推進している。職員間の情報共有システムを構築しようと思ったきっかけを聞いた。

教員と市民がフラットな立場で教育について自由に意見を交わす場「オモロー授業発表会」には、教職を目指そうとする学生や、若手教員の参加者もいる。教職の魅力を再確認する場としても役立ててほしいと、発起人の久本和明さんは話す。子どもの参加も大歓迎だという。そんな久本さんがいま、変えたいと着目するのは学校と社会の接続、特にキャリア教育だ。2023年には世界50カ国を巡り、その国の教育や文化、生き方や働き方と、人々の幸せとの関係をリサーチしてきたという。

ユニークな授業実践を教員らが持ち寄り、自由に市民と語り合う「オモロー授業発表会」は、市民の力で教育を「楽しく」変えることをモットーとして開かれる対話イベントだ。昨年11月の週末に東京都内で開かれたオモロー授業発表会には、市民が主催者となり約100人が参加。会場スタッフとしてボランティアに駆け付けた会社員の女性は「この時代に教育を何とかしなくては」と参加の動機を語った。こうした思いが、現役教員だけでなく元教員や教員を目指す大学生、教育NPO関係者、保護者など、さまざまな立場の人を結び付けている。

教員や保護者、地域のフリースクール運営者、大学生などが授業実践や思いを発表し、対等に語り合う「オモロー授業発表会」。2023年に関西から始まったこの催しは瞬く間に大きなムーブメントとなって、現在は北海道から沖縄まで全国各地で毎週のように開かれている。発起人の久本和明さんは独自の経営哲学で、アパレルEC販売を手掛ける企業の創業者として知られるが、なぜ教育に関わろうと思ったのか。そのきっかけは、1本の映画にあったという。

青森県むつ市の地域移行した部活動「むつ☆かつ」の吹奏楽部では、新しい部活動の在り方の模索が続いている。初めてのコンクールで東北大会出場という結果を残したが、指導する工藤守生氏は、現役の教員時代にも吹奏楽部の顧問として実績を重ね、また地域の吹奏楽の活性化にも取り組んできた。インタビュー最終回では、これまで培ってきた指導のポイントのほか、保護者との関わり方などについて聞いた。

青森県むつ市では、中学校の全ての部活動を2025年度までに地域移行する「むつ☆かつ」をスタートさせた。「むつ☆かつ」吹奏楽部で指導する工藤守生氏は、地域移行によるメリット・デメリットをそれぞれ感じているという。インタビュー2回目では、吹奏楽部の地域移行によって、中学校がどのように変化したのかなどについて聞いた。

部活動の地域移行が進められているが、取り組み方は各自治体によってさまざま、地域移行後にイメージする部活動の姿も人それぞれ――というのが実情だ。部活動の種類によって上位団体の仕組みが異なることもあり、混乱が生まれている。青森県むつ市は地域移行した部活動「むつ☆かつ」を今年度スタート。全ての部活動を2025年度までに地域移行する計画だが、今年度に「むつ☆かつ」に移行した吹奏楽部は、初出場のコンクールで県代表になり、東北大会に出場する実績を残した。これまで、中学校の教員として、また吹奏楽連盟の役員としてむつ下北地域の吹奏楽の指導に取り組み、現在は「むつ☆かつ」吹奏楽クラブで指導にあたっている工藤守生氏に、部活動の地域移行の現在について聞いた。